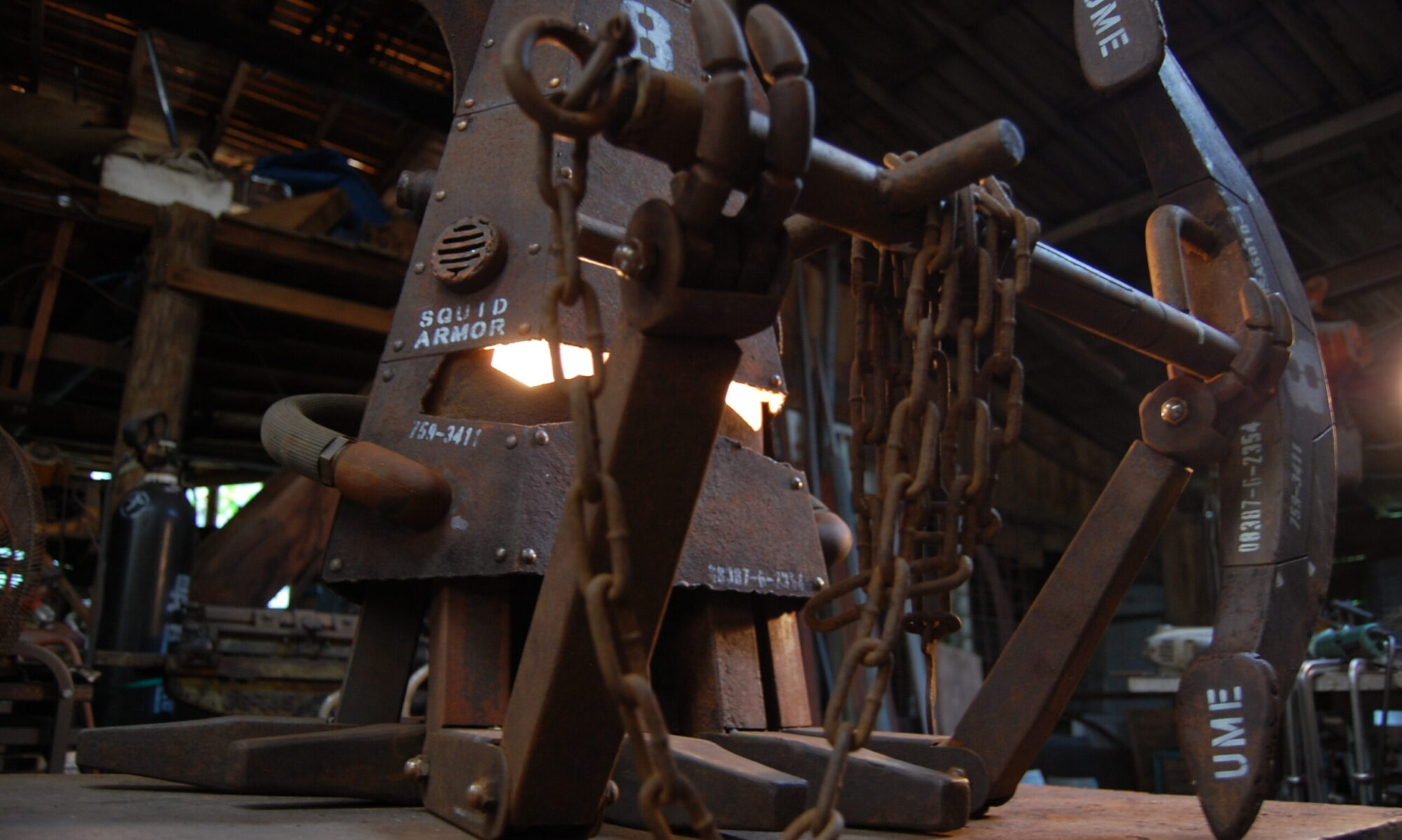6日から営業しています!
昨年は大晦日・元旦まで、営業していまして、
うちの店的には初めての試みでした。
というのも、今までは、
活イカ・活魚・鮮魚の仕入もままならないことや、
おせち料理を受注配送があったためなのです。
(昨年より止めています。)
で、定休日の5日まで休みとしていたのですが、
実際は、毎日なんらかの仕事が入り、5日6日7日とたくさんの仕出しのご依頼が入って、
激しい仕事量に追われたスタートでした。
子どもとの約束
昨シーズンからの子どもとのスケートに行く約束を、4日としていました。
当日まで何もなかったのですが、4日の朝の出発の間際になって5日の仕事の受注があり、
流石に、家族に仕込みを任せ(自分でできる段取りは組んでおきましたが)、スケートへ行かさせて頂きました。
23年ぶりのスケート
浜田にあるスケート場ですが、初めて行きました。
23年ぶりのスケートは、なんとなく覚えているもんですね。まずまずでした。
終始、子どもに付き添ってあげてましたが、
ローラーブレードで鍛えておいた上の娘は、なんだかんだ結構滑れるようになって喜んでいました。
激しい靴ずれに苦しみながらやったかいがありましたw。
山陰の繁盛店
スケートに行く前に、浜田市「菜の華」と、(結果的に)夕食で益田市「すし蔵」に訪れました。
両店とも日経レストランでも紹介されていた繁盛店「すし蔵」の系列店です。
「菜の華」は、色々感心させられます。和食バイキングのお店ですが、ほぼ全て手作りで、味は薄味ですが美味しいのです。
つい、必要以上に食べてしまうのはバイキングのマジックでしょうかwww
益田市のすし蔵は、家族でもたまに行きますので、知ってはいましたが、
日経レストランの記事を見た上で行くと、なるほどと更に感心させられることも多く、
業態は回転寿司ですが、外食産業で、子どもからお年寄りまでたくさんの方で賑わっているという事実・結果は、
同じ山陰エリアで商売する者としても勉強になりました。
例えば、本年からうちでも取り入れようと思っていたことを、普通にやっている点などは、
今まで、気づいていなかったというより、「うちはやらなくていい」と、どこかで思考から切り離していたのかもしれません。
両店とも訪れた時に、社長さんが来られていました。すし蔵では、中に入って握っておられ、笑顔でお客様と接しておられました。
社長さんは、私と同じ年ですが、いやいや、見た目の柔和な笑顔も貫禄も、力を感じました。
一番自分が刺激を受けた点は、両店共に、顧客の大半が地元であるという点です。
市場の性格上、そういう方向をとったかもしれませんが、
萩しーまーとの成長しかり、地元客に愛されてこそのクチコミと成長を感じます。
よく、うちで勘違いされる方も多いのですが、梅乃葉の土日祝日などの昼の営業を見ていると、
遠方の観光客ばかり相手にしているかのようにも見えますが、
平日は、地域で仕事をされるサラリーマンの方や、近圏の方々の食事が中心で、本当にありがたい存在なのです。
更に言えば、うちは、仕出しにも大きなウェイトがありまして、夜のご宴会等含めて、昔から普通にやっていることなんです。
土日祝日の昼の営業で来られている、遠方からの観光客の方々というのは、そもそも、全てが、プラスアルファ。
これも又、感謝です。
良い休日を過ごせました。
本年も、地元の方に愛され、遠方の観光客の方には期待に応えられる、そんなお店づくりに精進してゆきたいと思います。
宜しくお願いします。